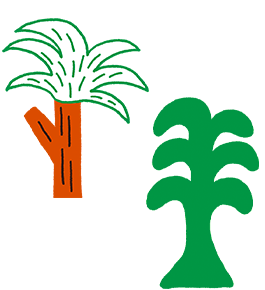「過疎」という言葉が生まれたと言われる島根県ご出身で、ローカルジャーナリストとして活動される田中輝美さん。2017年に上梓された「関係人口をつくる」では、島根県が先駆的に行っていた「関係人口」政策の実例を中心に、移住とも観光とも異なる都心と地方の人々の関わり方を紹介しました。現在は島根県立大学 地域政策学科にて指導にもあたられている田中さんに、地方から見た「関係人口」の現在地、また地元の鉄道廃線も一つのきっかけとなったという新しい取り組み、「美又共存同栄ハウス」について伺いました。
「関係人口」以前から存在していた地元出身者のふるさとへの想い

1999年に山陰中央新報社に入社し、地元の島根県を中心に2014年までの15年間にわたり地域を見つめ、新聞記者として取材し、記事を書き続けた田中さん。
2009年に転勤先の東京で出会った同郷の人々、就学や就職などで「ふるさと」を離れた方の多くが、意外にも地元に貢献したという熱い想いを抱えていることに驚いたそうです。
その仲間たちと「ネクスト島根」という会を立ち上げ、行政が募集していた地域活性のコンペに応募されたこともあったそうですが、県内在住でないこと、島根本社の企業ではないことなどもあって採用されることはなく、徐々に活動も停滞していった経験も。
一方で、地元出身の学生たちからは、絶妙な間合いで地域と関わる楽しさを発見したことも。当時、まだ言葉として生まれていなかった「関係人口」の担い手たちとの邂逅だったと述懐します。
島根出身の社長が経営する「炉端かば」や、「りげんどう」というお店が都内にあるんですけど、そこで島根出身の社長さんたちや学生さんたちとよく飲んでいたんです。学生たちが、地方とか地域に興味があると言っていました。理由を聞くと「旅では物足りない。観光は綺麗なものを見て、おいしいものを食べて、終わりじゃないですか。もっと人とつながりたいんです」と。地方とか、人が好きなら移住したらいいのにって言ったら、「そんなのハードル高すぎですよ」と返されました。あぁ、「旅と移住の間」がポイントなんだって、その時に思ったんです。
2016年に高橋博之さんが著書「都市と地方をかきまぜる」で、はじめて「関係人口」と明記し、提唱をはじめました。移住や観光とは異なる地方との関わり方、ボランティア活動も含め定期的に地方を訪れるような行動の情緒的かつ経済的な価値を説きました。 さらに同年、雑誌ソトコトの編集長の指出一正さんも著書「ぼくらは地方で幸せを見つける」で、関係人口としての地方との多様な関わり方を紹介しています。

この2冊と出会い、田中さんは「関係人口」という言葉に出会い、感動したと言います。
お二人の本は、どちらかというと、都会から関係人口をとらえた言葉だと感じたんです。これを地方の視点からとらえて、都会の人たちとつながって、それぞれの課題解決できたら最高だなって思いました。そして、自分たちがネクスト島根でやっていたような活動が、関係人口だったんだということに気が付いたんです。関係人口っていう名前が当時からあれば、あの時のみんなの想いは、活かされたかもしれないと思ったんです
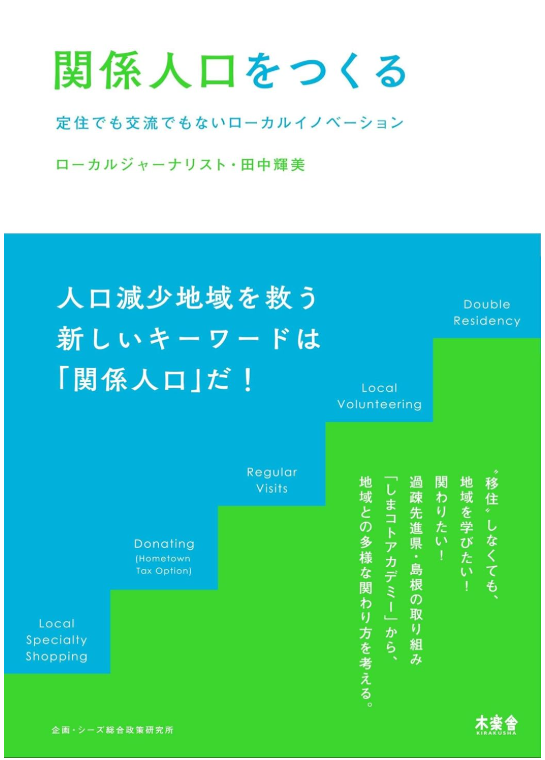
関係人口の概念を、地方側からも光を当てたというのが、多分私の役割だったと思います。関係人口を地方側の課題解決にもつなげることができるよ。地域の外に仲間がいるよって、地域の人たちに伝えたくて頑張って書いたんです。書いて一番多かった反応は、意外にも「自分のことを書いてくれてありがとう。救われました」という関係人口側からの声だったんです。
都市と地方という離れた場所で生活する人々の多様な関わり方が、「関係人口」と名前が付いたことによって顕在化し、しっかりと定着してきたと田中さんは言います。国も地方創生の一環として政策として取り入れるなど、行政や地方自治体が関係人口創出の旗振りをはじめました。概念が定着する一方で、自治体など地方側の過度な期待や移住定住政策の手段として関係人口創出を目指すことへの違和感を田中さんは指摘します。関係人口という言葉が生まれて間も無く10年。島根を拠点に活動を続ける田中さんに、「関係人口」の現在について伺いました。
よそ者と面白いまちづくりをしていると移住者が増える?「関係人口」の現在地

衝撃的な内容で話題となった「地方消滅」(増田寛也著)に端を発し、消滅の可能性がある自治体名が公表されるなど、人口減少が待ったなしの現実として突き付けられたのが2014年でした。当時の安倍晋三内閣は、新たに地方創生相を設け、初代大臣として石破茂現首相を任命しています。
それから10年。2024年にスタートした石破政権は、「地方創生の再起動」を掲げ、その重要な施策として、地方への移住促進をあげています。移住・定住と関係人口の関連性について、田中さんに伺いました。
関係人口を移住・定住促進のための手段とすることは違うと思っています。アンケートや調査からも分かっている通り、関係人口から移住へ進む割合は限られているからです。移住を考えている人たちは関係人口とはまた別のところに大勢います。その人たちが、移住先を検討する時に、関係人口と一緒に面白い地域づくりをしている地域が候補にあがると考えています。外からの移住者となる自分たちも地域に受け入れてもらえそうって感じるのではないでしょうか。外部人材と面白い地域づくりをしていることで、結果として移住者が増えるっていう傾向があるようです。だからと言って、関係人口を移住定住の目的のための手段としないでほしい、目的ではなく結果である、というのは、繰り返し講演会などでも話しています。
産直サイトなどを通して生産者や現地メーカーから食品や特産品を購入することや、ふるさと納税(寄付)を利用するような現地を訪れないライトな関わり方も、広義において関係人口に含まれています。一方で、現地に赴くという直接的な行動を伴う、地方との濃い関わり方として注目を集めているのが「二地域居住」や「二拠点生活」と呼ばれるライフスタイルです。今までの生活の場を維持しながら、地方に定期的に通い、その地でも一定期間生活をすること。都心と地方の両方の多様な価値観に触れながら、暮らしや仕事を続けることができます。完全に移住するよりはハードルが低く、働き方も変化し多様化する価値観を持つ生活者には魅力的な選択肢となっています。
一箇所だけに住んでいなくたって、地方でも面白く活動できると気づいた人が増えましたよね。ひとつのモノサシによる格差論じゃない、都市と地方の特徴の違いに価値を見出しているのではないでしょうか。私は、二地域居住がひろがっていってもいいし、関係人口が増えていってもいいし、結果として都市の人の課題解決と地方の人の課題解決が一緒にできるのであれば、社会全体にとってプラスになると思っています。
「地方消滅」の衝撃から丸10年。実際に人口がピークアウトした現代日本において、これからを担う若い世代、学生の方々はどのように感じ、考えているのでしょうか。
若い人は若い人なりに人口減少社会をどうしていこうかと悩んでいますよね。大人たちからそう期待されていることも大きいと思います。そんな学生たちと、「関係人口って地域間の人材のシェアなんだ」という話をすると、ものすごく共感してくれます。
さらに、自らの意思で地方と関わる人々も増えているようです。
自分が関わる面白い場所がローカル(地方)だ、というライフスタイルを選ぶ人たちも増えているようです。地方に貢献したいとそれほど強く意識していなくても、結果的に貢献につながるような関わり方をする関係人口が増えている。特に若い人たちに多いと感じています。
課題が山積する地方に、その課題解決の役に立ちながら、地域の自然や文化に触れ、そして人々と繋がることの面白さや楽しさ。そんな地方との関わり方をライフスタイルとして選択すること。濃淡はあれど関係人口は着実に定着し、すそ野は広がりつつあるようです。
この都市側のライフスタイルの一つとする地方との関わり方と、地方側の関係人口に期待する温度差や切実感のギャップの大きさが課題となることもあるのかもしれません。
関係人口って、ある意味、絶妙な名称だと思っていて、やっぱり関係なんですよね。関係があるからモノゴトが動いていく。都市側も地方側もお互い信頼関係を作るって言うことを忘れないでほしいです。そこからしか始まらないし、それがないと何も始まらないんですよ。
しかしながら、人口減少社会による差し迫った課題を抱える行政側の考え方やアプローチの方法を危惧していると田中さんは言います。
人口減少対策!とにかく今、人手が足りないから、なんとかそこに外の人を頼ればいい。何でもボランティアを募集しようというようなアプローチが増えているようにも感じます。関係人口って、そもそも人と人の信頼関係があったうえで、お互いの課題が解決されていくという概念だったのが、どちらかというと地方側の視点や都合が強くなりすぎているように感じています。両者がメリットを感じるような政策にしたほうが良いのにと感じることも増えています。
関係人口づくりに関連した活動は、多種多様。関係人口創出に課題を抱える地域もあれば、関係人口を受け入れる催しや体験プログラムの現場の運用が課題という地方も多いようです。田中さんは、互いに小さなつまずきや失敗を重ねながらも、一緒に汗を流すからこそ生まれる信頼感が関係人口づくりには何よりも大事だと言います。その結果、自然と両者それぞれの「役割と出番」が生まれてくるのだとか。
お願いするよりも、「これやりましょうか?」という主体的な言葉が出てくるのは、草刈りなどの農作業でも、お祭りの手伝いでも、何かしらの行動を共にしたからこそ生まれる信頼関係があってこそのようです。
「関係人口」という概念が定着する一方で、都市側と地方側それぞれのニーズと関係人口に期待することが変化している事実。そのギャップを受け止めながら両者が歩み寄りたくなる工夫が、これからの関係人口政策には必要なのかも知れません。
後編へ続きます。
取材日:2024年12月20日